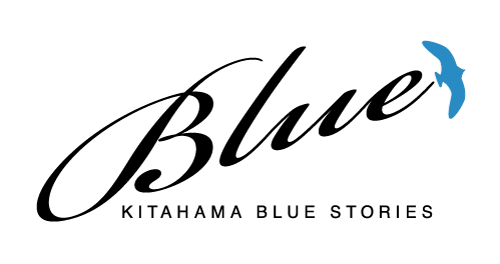vol.10 画家 山口一郎さん たくさんの「こと」や「もの」があふれる今、作り手の想いと使い手の心がつながる奇跡。瀬戸内の小さな町で暮らし、ここにある風景、文化、素材と向き合い、ものづくりにこだわりと情熱を注ぐ作り手の方々をご紹介します。 彼らの美意識やものづくりの喜び、遊び心などが詰まった言葉を大切に集めてそれぞれのストーリーを発信していきます。 第10回は、画家 山口一郎(やまぐちいちろう)さん。香川にやってきて早20年。全国各地の展示会やイベントで忙しく飛び回り、日々新しいことに挑戦する一郎さんの画家としての原点をお話しいただきました。 ーまず 始めに今年で何歳になられますか? 今年で55歳になります、あっ6だって56歳でした(笑) ※後日談として、本当は55歳とのことです。 ー画家になろうと思ったきっかけを教えてください。 東京でイラストレーターをやめて、実家の静岡に帰ってパン屋の仕事をしながら好きなように大きな紙に絵を描くようになって… その日描いた絵を、ネットで当時やっていた「ウナギコンピュータースタジオ」っていうブログに載せて日記をつけていたんですけど、ブログ読んだ方から感想のコメントを貰うようになったんです。タイミング良く東京のDEE’S HALLさんに絵を見せに行く機会がありまして、展示をしませんかとお誘いを受けてそこから「画家」と名乗るようになりました。 ーそれまでは趣味の一環だったんですか? そうですね、画家って言うよりも公表することの無い絵をひたすら描いているだけの人でした。バイトをしながら…まあ趣味ですね。 ー昔から絵を描くことは好きだったんですね。 うん。漫画ですけど、好きな漫画の絵を真似して広告の裏に描いたり高校卒業したぐらいの頃に漫画家になりたくて漫画を描いて出版社(講談社)に持ち込みしたことがあって…結果は全然ダメでした(笑) ーちなみにどんな物語りを描いたんですか? 尾崎豊の詩みたいな話を描きました。「学校なんて…」みたいな気持ち悪くて実家のどこかに閉まっちゃいました(苦笑い) ー昔好きだった漫画家はいますか? 望月峯太朗さんの漫画が好きでして、「バタアシ金魚」が一番好きでその絵をずっと真似していました。当時すごく好きで漫画家になろうと思ったときはずっと峯太朗さんの絵をみてました。 ー元々は画家ではなく漫画家志望だったんですね。 そうです。でもストーリーが描けないから無理だったんです。あと漫画っていろんなキャラクターや風景を描かなきゃいけなくて、それが上手く描けない…今は漫画より絵本を描いてみたいです。 ー東京の学校に通われていたんですよね。 東京のセツ・モードセミナーに通っていました。絵を描くことが好きだからとりあえず絵の学校行ってみよう、でもお金ないから安いところ行こう、みたいな感じで。入学がくじ引きみたいなところだったんで入学金も安くて、僕でも通えるかなと思いました。 ーどんなカリキュラムがあったんですか? なんかね、見て盗めっていう感じでしたね。友達や先生の描いている絵を見て。校長先生がデッサンが得意な方でしたので「俺うまいだろう」って一緒になってデッサンしたり、週に一回水彩画で静物画を描いたり、あとは好きなものを家で描いて発表したりひたすらその繰り返しでした。でも、この学校に入学してはじめてデザインの分野を知り得ましたね。 自由な学校なので来なくなる人も多かったんですけど、あとは他の学校行きながら来てたり年齢の幅も広かったです。下は中学生から来ていて、なんだか絵の塾みたいなところでした、2年ぐらいの学校だったんですが卒業資格もなかったです。 僕も1年ちょっとぐらいで出版社のマガジンハウスに絵を持っていってそこで「olive」の雑誌にデビューして学生時代からイラストレーターの仕事が始まっていました。 ーマガジンハウスさんを知ったのはどのタイミングだったんですか? 最初はイラストレーターの仕事もよく分かってなくて、自分の作品をファイルしていたんですけど一番自分の絵を載せたい好きな雑誌がマガジンハウスの「olive」だったんです。そこに自分の作品集を飛び込みで持って行ったら採用されました。 ー戦力になる人だったら即採用だったんですね。 当時は飛び込みで持っていく人が多かった時代でしたね。雑誌の紹介コーナーの地図を描いたり、ファッションのアイコンの絵だったり企画の絵を描いたり色んなイラストを頼まれましたね。専属ではなく依頼が来たらテーマに沿った絵を描いていました。 ー「olive」って当時は誰もが知る人気の雑誌でしたよね。 うん、かわいくてね。女の子の10代~20代向けのファッション雑誌で、僕がデビューした当時の表紙はまだデビューしたての宮沢りえさんでした。 ー「olive」の雑誌以外にも何か手がけられていたんですか? 「POPEYE(ポパイ)」の表紙もしていました。まあ、全体的に一通り仕事していたと思います。「ターザン」や「ブルータス」…一番仕事していた雑誌は当時の「ダ・カーポ」っていう雑誌ですね。マガジンハウスの中じゃファッション誌って言うよりも、政治とか今で言う週刊文春や週刊新潮みたいなマガジンハウス版でした。文字が多い雑誌ですけど、そこにちょっとイラストが入った表紙を1年間ぐらい描いたりとか中の絵も結構いっぱい描いてたり、別冊の絵も全部担当したりとか色々ですね。 ーファッションが好きなのかと思ってました。 いえいえ、僕を採用してくれた担当の方が「POPEYE(ポパイ)」とかをしていてそのあと「ダ・カーポ」の編集長になったんですよ。「山口、いっぱい描けよ」って言って描き始めた時に僕、マガジンハウスに住み着くようになって(笑)そこで2、3年ぐらいかなほとんど一週間土日以外はマガジンハウスをウロウロしている人になって… ーお家はあったんですよね??? 家あったんですけど、あの~家より快適というか…ごはんはタダで食べれますし、ウロウロしているとお酒を飲みに連れていってくれたりエアコン効いていて、発行している雑誌は全部貰えて「天国」でした!そして会社が銀座にあったので立地もよくウロウロするにもいい。楽しかったです(笑) ーマガジンハウスさんの仕事で一番苦労したことと楽しかったことはありますか? やっぱりね一番苦労したのが、「olive」でデビューした時かな。憧れの雑誌だったんで、初めての仕事で急に手が動かなくなっちゃって、涙も出てきてすごく怖くなったんです。「これ、全国誌で色んな人が見るんだって」思って恐怖になりました。手が動かなくなったのはその一回きりで、もうダメかもしれないと思ったんです。普段描いていないマップの絵なので苦手な分野ではあって、克服までに結構長い時間がかかって、気持ちを落ち着けながら提出してOK貰えたんですけどすごいプレッシャーでしたね。仕事が終わったあとみんなでお酒を飲むのが楽しかったですね(笑) 楽しかったこととはまた違うかもしれないんですけど「タンカレー」(お酒のジンメーカー)のラベルジャケットのコンペがあって、その時にマガジンハウスのコピー機で10分ぐらいで作ったんですよ。そしたらそれが入選して、それで、大きな会場で大きな画面に1つ1つ作品を投影してるのを観て「これ10分かかってないんだよな~」と思って笑ったことはあります。 審査員の方から「これってデジタルで描いているんですか」と聞かれてコピー機で拡大してペンで色つけただけなんだけどな~って(笑)。 ーちなみにどんな絵を描いたんですか? なんかね、円を何個も重ねて抽象的な感じで作ったんです。そこに色を重ねたのがデジタルぽく見えるんですけど、それが何百人や何千人と観られる会場の選考10人ぐらいに選ばれまして…で、発表されていたのを見て「絵って時間じゃないな」と思いましたね。大賞には選ばれなかったんですけどね。 ーマガジンハウスには何年勤められていたんですか? たぶん、4、5年いたとおもうんだよね。仕事を辞めて静岡の実家に帰る寸前まで広尾のこどもたちに絵の教室の先生をやったりとかしてました。デザイナーさんの知り合いの男の子なんだけど、絵が好きな子がいて、なんか先生を探していたらしくて「一郎行け」って言われて行くようになったんです。 ー絵画教室の先生されていたんですね。 先生というか、子どもたちと一緒になって遊んでいました(笑)当時はその子の友達で絵画教室通っていたけど嫌になってしまった子や絵の好きな兄弟とか知らない間に口コミで広がっていて、その内塾の先生からうちの塾で週末絵の教室やってほしいと言われて教えていましたね。 ー今も色んな展示会でワークショップされていることが多いですが昔から、結構こどもたちと一緒になってすることが多かったんですね。 うん、友達が小学生しかいない時期もありました(笑)休みの日も携帯に電話かかってきて、教室のこどもたちと公園で自転車でドリフトしてたりしましたね。 ー他のコンペディションには応募されたりはしたんですか? 何のコンペか忘れてしまったんですが、副賞でフランスかニューヨークに行ける分に賞をとったことがあってそれでニューヨークに行きました。全く英語が喋れなくてお母さんに「行きたくない」って泣いたんです。 ー海外は行きたくなかったんですか? 行きたくないです。2人だったらまだいいんですが1人なると怖いじゃないですか。 ー何歳ぐらいの話だったんですか? 20代半ばぐらいの年齢ですね。当時はまだ飛び込みでファイルを見てくれるギャラリーもあって、滞在中に落書きばかりしてたから、それを纏めて、soho(ソーホー)にあるギャラリーのひとつに持って行ったら見てくれて、紙を渡されたんです。僕、英語が全然読めないから、ホテル帰って日本人観光客のガイドさんに翻訳してもらったら「何日にオーナー来るからその時ファイル持って来なさい」って書いてあったんですけどその日、日本に帰る日で時間が合わなかったんですよ…。 2回目にニューヨークに行った時はギャラリーはあったけど、見た目が全然変わっていて見てくれなさそうでした、勿体無かったですね。 ーよく飛び込みで持っていけましたね。 ねえ、行く時は泣いていたのに(笑)ファイルの前に英語で「僕、英語わからないですけど絵を見てもらうことは出来ますか」って一生懸命辞書で英語を調べて書きましたね。 ー時代ですね。グーグル翻訳とかない時代ですよね。 そうなんです、だから結構怖かったなぁって。地下鉄とか治安が悪かったので、日中は地下鉄を避けて地上を歩いていたんですが首からカメラ下げて、手には地図持ってて感じでいかにも観光客ですっていう格好で歩いてたんです。そしたら3人ぐらいの男の子がずっと後ろをつけてきて肩ドーンてされましたもん。それを無視して下向いて歩いていたら、離れていきましたけどちょー怖かったです…やばかったです。 ー海外で絵を展示したことはありますか? アメリカに2回目行った時に、ブルックリンにある「Blue Sky Bakery(ブルースカイベーカリー)」の壁に、お花の絵を6枚ぐらいだったかな飾ったことがあって、結構すぐに買い手がついたんですよ。 女性のお客さんで、旦那さんにクリスマスのプレゼントでひまわりの絵を買いたいってお客さんがいたんです。海外での絵の販売はこれが初めてだったんですが、「あなた日本人だったのね」と言われたんです。絵を気に入ってくれて買ってくれた思うと、何だか海外でも認められて気がして嬉しかったです。 ...
続きを読む
vol.9 木工作家 加賀雅之さんたくさんの「こと」や「もの」があふれる今、作り手の想いと使い手の心がつながる奇跡。瀬戸内の小さな町で暮らし、ここにある風景、文化、素材と向き合い、ものづくりにこだわりと情熱を注ぐ作り手の方々をご紹介します。彼らの美意識やものづくりの喜び、遊び心などが詰まった言葉を大切に集めてそれぞれのストーリーを発信していきます。第9回は、木工作家 加賀雅之(かがまさゆき)さん。サラリーマンを経て木工の道に…飾らず、背伸びせず、正直に。作品に表れる真っ直ぐな人柄を感じながら、ものづくり人生となった加賀さんのストーリーをお話しいただきました。ー木工作家になろうと思ったきっかけは何ですか?普通に大学を出て就職をしてサラリーマンをやっていたのですが会社の方針や仕事の仕方に疑問がずっとあって、いつか破綻しちゃうんじゃないかって感覚があったんです。会社は右肩上がりじゃなきゃいけないし、借り入れをしたら返済する事が義務になって、無理や無茶がはじまって人を雇ったらその分また生産性を求められて…ずっと成長し続ける事は結果、自分たちの首を絞めているような感覚。右肩上がりにこだわらない、借金をしない、必要以上に大きくしない。会社で感じた違和感を逆にとらえて考えたら、自分一人でやるのが向いているんじゃないかな、と結論になりました。
ーその時に木工作家になろう!と思ったんですか?
木工をしようとは特に決めてなかったです。高松でサラリーマンをしていた時、嫁さんが職業訓練校の資料をもってきてそこが岐阜県飛騨高山の木工科のものだったんです。入校すれば一年間失業保険を受けながら専門的な技術を教えてくれるから行ってみようよ!と。その時結婚していたのですが、有給をとって飛騨まで試験を受けにいき合格したのでじゃあ行くかってことで木工を始めました。 ー木工があってのスタートではないのですね。そう、木工を最初に考えていたわけではないんです。自分一人で仕事をするときに、物を仕入れて売るのは運転資金も要りますし、個人でするのは現実的ではない。それよりも自分で製造業としてものを作って売る方が自分の匙加減というか、思うようにやれるんじゃないかというイメージがありました。ー木工以外のほかの選択肢もあったんですか?どうだったんだろう…嫁さんが持ってきたのが木工だったから。やるんだったら木工かなとか、そんな話はしていたのかも。ただ陶芸や他のことをやろうとは全然思わなかったですね。もともと嫁さんがサラリーマンをあまり長く続けさせたくなかったようであんたそんな仕事続けていたら早死にするでってよく言われていました。 ー素質を見出してくれたんですね。どうだろ~(笑)
ーもともと作家になるっていう感覚は自分にありましたか?
どっかではあったのかもしれない。いつかそういうのが出来たらなぁとは思っていました。もっと遡っていくと高校生の時に芸大とか受けたいなと思ったことはあるんですよ。ただ調べてみたら学費とかが高すぎて現実的ではなかったんです。なのでとりあえず普通の文系の大学に行きました。見るのも作るのも描くのも好きだったけど特別人より何か得意ってわけでもなかったですし、手先は器用な方でしたが、芸術系で戦ったことはないから...ふわっとしていたかな。10代20代はそんな感じでふわっと過ごしてました。でも、どっかで何かやりたいとはあったのかもしれませんね。
ーそしたら木工自体も0(ゼロ)からのスタートだったのですか?完全にゼロからですね。何も知らずに始めました。訓練校は期間が1年間、同学年が22名ぐらいで、社会人や若い方いろんな人がいましたね。そこに交じって実際に集中してやってみて、あぁなんか自分に向いているなという感覚がありました。 ー向いているなと気づいたのはどれくらいなんですか?4月に入ってゴールデンウィークぐらいまで延々、かんなの刃を研いでいて…本当基本的なことですが、最初はぜんぜん研げないんです。刃は丸くなるし全然ダメだったのが毎日していくとゴールデンウィーク前に急にびたっと刃が付くようになって…その時にちょっと合ってるのかも、と。クラスの中でも感覚をつかむのは早かった方ですね。色んな基本的な手加工を習っても、割と飲み込みが早い方でした。
ーそこから木工作家の道が始まったのですね。 とはいえたった1年間、学んだことで仕事にするのは難しくて、結婚もしているし、生活もしていかなくてはいけないじゃないですか。なので卒業後は、飛騨の木工会社に就職をしました。6、7年働きながら同じ訓練校で所帯持った同世代の2人と一緒に3人で豚舎だった建物を借りて、1年掛けて綺麗にして、中古の機械もお金を出し合ってそろえて、実際に自分でモノづくりを始めたのが2007、8年頃ですね。そのころは木工会社に勤めながらだったので加賀雅之の名前ではなく屋号「semi-aco」で活動していました。
ー屋号の「semi-aco」の由来は何ですか?semi-aco(セミアコ)はセミアコースティックギターの略称ですね。アコースティックギターは中が空洞になっていて弦の振動を本体の中で反響させて楽器自体で音を出すんだけど、エレキギターっていうのはマイクが付いてて音が出る。ちょうどその中間のセミアコースティックは中にマイクがあって、本体だけの音も、マイクを通して大きい音も出すことが出来るっていう楽器。ハイテクとローテクの中間みたいな感じで、僕が木工でやりたい工業製品と手工業のいいところを取り合って出来るモノ、そんなイメージでこの名前にしました。手仕事っていうのは必要で大切だけど、数を作るとなると全て手仕事は難しいし、その分単価も高くもなる。手仕事だから凄い!訳じゃなく、適材適所で、ちょうど良い塩梅があるはずなんです。工業製品には工業製品のいいところがあって、機械の力をかりて出来る仕事と手仕事にしか出せない仕事があって、そのバランスを取りたいんです。ー工業製品と手仕事の間に加賀さんのモノづくりがある?そうそう、もともと工業製品好きですしね。同じものがいっぱい並んでいるとか、どこか幾何学的なものが好きだったりとか、歯車とかも(笑)逆にあまりにも自由過ぎるのはないかもしれないですね。 ーアート的なモノづくりは加賀さんのイメージにはないですもんね。 結局僕が作りたいのは道具なんです。アート的な世界になると座れなさそうな椅子でもこれは椅子ですと言ってしまうんですよ。でも僕の感覚では、それは椅子じゃないよねってなるんです。自由な発想、アート的なモノづくりでもやっぱり使う事が出来る道具であって欲しいんですよね。インスピレーションを貰うのは工業製品や昔の道具から来ることが多いかもしれない。
ー作家としてここは譲れないな、と思うところはありますか? 良くも悪くも好き嫌いがはっきりしてるから、流行りがあったとしても自分が苦手なら絶対にやらないですね。ー絶対?絶対です(笑)これは自分がサラリーマンを経験しているからわかる事かもしれませんが世の中の8割の人が良い!というものは大体大手がやるんですよ。そうなると、僕らみたいな個人では手に負えない。それだったら、流行ってるからやってみるというより、自分が本当に良いと思うものを作り続けていれば、たとえそれが5年売れなかったとしても、もしかしたら6年目に売れるかもしれないし、そっちの方がなんか説得力ありますよね。
ー現在木工の道に進んで何年ぐらいになるんですか?木工を始めて18年目になりますね。semi-acoとして始めたのが2007年、2008年ぐらい、そして岡山に来て12目年になります。当時は置いてもらっているお店とかも少なくて、クラフトフェアとかを全国で開催していて作業場で作りためたものをクラフトフェアにもっていっていたんですが、やっぱり木工会社を務めながら作家業をするのに限界を感じまして。数が作れないし、やるなら1本に絞ってやらないと、と思って岡山で始めました。ーなぜ岡山で始めたのですか?嫁さんの出身が岡山の児島で僕が京都出身だったんです。独立するなら住む場所と作業場所が一緒の方が金銭的にも良かったし、木工の加工機械を回すとどうしても大きい音が出るので街中では難しい。で、限られた中で考えると田舎の母屋と離れがあるような物件がいいよね、と。京都は山の中の物件を探しても家賃が高かったんですよ。で「うゎー、高いなぁ~」って…2人とも西日本の出身なので兵庫や大阪の方まで物件を探してましたが、引き寄せられるように最終的に岡山にたどり着きました。田舎暮らしがしたいとかはないんだけど、必然的に田舎暮らしになってましたね。ー加賀さんのお家テレビもないし田舎に一種の憧れがあるのかと思ってました(笑)違うねん!意識高い系に勘違いされそうやけど結構普通でいいのよ(苦笑)テレビは確かにないけど、もらったテレビが壊れてしまって、ないならないで大丈夫だっただけ(笑)機械の音が出る仕事だから隣に家もなくて、夜中に大きい音が鳴っても大丈夫な田舎暮らしに結果的になっただけなんです。東京で働いていたこともありますけど、別段都会が生活しずらい、とかもなかったですね。ただ子育てを東京でやろうとは思わなかったかな…。
ー作品を作る期間はどれくらいかかっていますか?よく聞かれるんですが、単純に木を板にして彫る作業だけだったらonigiri皿なんかは1枚30分もかからないです。けど、その木の板を作る前に丸太を板状に挽いた材料を買ってくるんですが、木って反ったりねじれてたりするんです。木を買ってきたら作るものよりも一回り大きい状態に切って、重ねて置いた状態で少しづつ削って真っ平らに近づける下ごしらえが1か月以上掛かってきます。 製品になっても保管している環境や空調によって反ったり木が育った環境によっても反りが違いますね。山の勾配が急な斜面に生えている木だと一方向にストレスがかかっていてねじれや反りになるんです。それをほぐしながら均一にしていくっていう感じです。 ー作品にする前の素材から手をかけているんですね。木のサイズが決まっていますし、割れや節もあるのでどこまで有効的に無駄無く使えるか、木材を扱うのは引き算の仕事になります。一度切ってしまうと元に戻せませんから制限がある素材なんです。
ー工程で一番楽しい所は何ですか?仕上げの工程でオイル塗っている瞬間ですね。それまでは木くずまみれなんですが、オイルを塗った瞬間木の器になるんです。艶が出て木の色味もグッと強くなって、出来た~って感じるんです(笑) ー加賀さんといえば彫り、彫りの工程が好きなのかと思ってました。長年しているので、手や体の感覚が覚えていて、自分が機械になった気持ちですね。その作業に没頭している間は色んなこと、いつも別のことを考えていることが多いです。集中してるわけでもなくて、機械みたいな感覚ですね。 ー木を彫ることに対しては緊張しないんですか。あまり緊張はしないかな。でも、料理するときの食材と一緒で木は生き物だと思っています。そこに刃物を入れるのでごめんなさいではないけどちゃんと使わせてもらいますと思いながら扱っていますね。ご飯食べるときの「いただきます」と同じ感覚です。ー木が生きているって言う感覚は木工作家さんならではなんでしょうね。そうかもしれませんね。土やガラスや金属より生々しい感じ。生きたものだし、しかも自分より長く生きた年上の存在ですからね。だから切れる刃物で、なるべく木に負担を掛けずに切りたいとは思っていますね。
ー使う道具はこだわっているんですか?
本当はそうしたいですが、作業場にある機械は中古品ですし工具もバラバラですね。お金もないので仕事で必要な道具をひとつひとつ買いそろえていった、という感じです。中古の物もあるし、人から譲り受けた物もあります。拘る方は好みのブランドで揃えるんでしょうが僕はそれよりもちゃんと研ぐ方にこだわっています。安い刃物でもちゃんと研いでメンテナンスすれば使えない道具はないですからね。手工具はメンテナンス出来るんですが機械は難しいですね…飛騨時代からお世話になってる機械屋さんに電話して、どこが悪いのか教えてもらいながら自分で直して使っています。
ー加賀さんの工房にはどれくらいの機械があるんですか?
色んな使い方ができる汎用機(はんようき)を8~9ほど置いています。大きい工場には専門の作業が出来る専用機(せんようき)がありますがそれではきりがなく、スペースの関係もありますしなるべく色々と使い回しが利く機械を選んでいます。新品で買う事は資金的にも難しいので飛騨にいる時に、独立に向けてある程度見繕っておきました。産地なので機械の中古品もよく出回るんですよ。それを岡山に来た際に一緒に送ってもらった感じですね。ー工房に籠る事も多いかと思いますが、作業中音楽とかかけられたりしますか?いつもラジオを流しています。FM岡山とかレディオモモしか電波が入らないけど…音楽も好きですよ。ただCDラジカセを持ってはいますが、わざわざ手を止めないといけないし、埃だらけになるのでやっぱりラジオかな。最近スマホデビューしたのでアマゾンミュージックとかスポティファイとかほんとうは聴きたいんですけどね。嫁さんがうん、と言わん限りは…ね。なかなか思うようにはいかんわ(笑) ーちなみに好きな音楽は???今はズーカラデルとかハンバードハンバートとか。竹原ピストルとか、昔の星野源も好きですね。今の星野源も好きだけど、昔のもがいてる感じの時が好き。全然何でも聴きますよ。サーフミュージックも好きやし。ロックとかポップ、でも縦のりじゃなくて横のりが好きです。 ー息抜きはどんなことされていますか。バイクで近所の山を走ったり、って言ってもツーリングって程でもなくて、ほんま近くのダムに行ってカップラーメンを食べて帰る。まあ、ピクニックに行く感じですかね。スランプみたいなのはないんですが、なんか、今日は怪我しそう…とか、なんか、嫌な感じがする…って思う時があるので、そういった時はおとなしくパソコンに向かって古い車をレストアしてるのをYouTubeで観たりしています。
ー「自分らしい」と思う確信があったのは始められてどのくらいでした?また名刺代わりになった瞬間とかはありましたか?確信か…売れてるものとか売れそうなものを作る気は元々なかったから「自分がやるんやったらこれやな」っていう感じで作り始めて…そうやね、10年くらい前かな、人気のある方がお皿を使ってくれてて、それをインスタにアップしてくれたらしくて、それを見て買いにいらした方がいた時かな。自分の彫りに名前が付いた感じ。
ー作品へのこだわり、彫りカタチ、使い勝手などありますか?彫りやカタチは自分の中でいいと思った物はありますが、基本は脇役であってほしいなと思いますね。onigiri皿やったら、おにぎりをのせて初めてonigiri皿になりますよね、主役をうばわずに引き立て役になるように、とは考えています。自分の展示会でも自分の作品の上にお皿やカップ、そのお店にある物をのせて引き立て役として使って下さい、とお願いしているんですが、感覚としては作品を作っているのではなく、生活の「道具」を作っている感覚ですね。自分の作品です!ではなく、他の作品があって使われて初めて活きる物であって欲しい。暮らしの中、人の営みに添う脇役がいいんです。 ー作品のアイディア、影響を受けた方はいらっしゃいますか?工業製品がもともと好きで直線的な物の方が好きで、幾何学模様のようなデザインが好き。影響を受けた方…ん-、べタ中のベタやけどイタリアの工業デザイナーのジョルジェット・ジウジアーロの車とかすごく好き。ベタすぎて恥ずかしいわ…昔直線的な車をデザインしてて、影響というかそういうのが好きかな。好きな作家さんもいるし、作家さんの物を買う時もありますが、工業製品ぽいデザインを選ぶかも。無意識に。手仕事ですから!みたいな自己主張が激しい物はあんまりかな…最近いびつなカタチのお皿も作ってるけど、いびつというカタチをめっちゃ考えますね。ただそうなりました、というカタチではなく、「いびつ」をたくさん描いて、そのなかの一番好きな「いびつ」をお皿にします(笑)そしてその「いびつ」をいくつも作ります。毎回違ういびつさではないですね。職人と作家とか、アーティストのくくりは難しいやけど、たぶんアーティストの人はその時一回きりのモノづくりはあり得るけど、職人さんはそうじゃない、図面を渡されて何百個と作れるのが職人さん。で、僕らは図面を描いたり、デザインまでやるから作家と呼ばれる。でも一回しかできません、というのは僕の中ではあり得ないから、自分が決めたカタチはいくつも作りたいですね。
ー今まで作ってるカタチの中で、一番のお気に入りは? お気に入りか…ん-、イチリンザシかな、やっぱり。息子が小っちゃい時にその辺の花をちぎってお母さんに「はい。」って渡してたやつを飾れるようにしたいなと思って作り初めたんです。木工会社に勤めていた時に出てた廃材から作りはじめたのがイチリンザシ、カタチも今と一緒ですね。当時も、今もですが、木工旋盤があれば丸いカタチの物を作れるのですが、持ってないので、持ってる機械でフリーハンドで最初作って今でも作ってます。もう何千個作ってんのかな…めっちゃ作ってますね。 pan皿もonigiri皿もあれはあれで作家として認知してもらえた気がするからやはり想い入れはあります。pan皿、onigiri皿があったからこそそれをベースに水平転換で最近は縁のあるお盆を作る事が多いですね。
ーでは今回の展示会について、どんな展示会にしたいですか?今回はお皿メインでなるべく、定番物から新しい物もちょっと混ぜながら、ほぼほぼフルラインナップを予定しています。blue storiesに普段あるガラスや焼き物など他の作品と一緒に組み合わせて展示してもらえたらいいかなと思います。 ー展示会へご来場いただくお客様へのメッセージは?メッセージか…でもいつもショップカードにも書いてあるけど、ちょっと温かく思ったり、ちょっと暮らしがゆるんだりするような、お家に持って帰って、ちょっと家が明るくなったりとか、心地いいと思ってもらえたら嬉しいですね。お皿一枚増えただけで朝ごはんが楽しくなったりとか、今日あのお皿であれ作ろう!って思えるのは日常生活の中で大事な事じゃないですか、そういう事の役に立てればうれしいなと思いますね。僕の場合は定番としてシンプルに同じものを使う事が多いから、自分が作る物にも派手さや最先端なものは必要ないのかなと思っていますね。 ー素直にちゃんと生活する道具としてのお皿なんですね。そう、劇的に変えなくていいから、ちょっと幸せになってくれたらいいな、と。ちょっとでもすごいことだと思うけど、劇的に変えられる程の力は僕にはないから。
ーワークショップについて、前回に引き続き、今回もされますが、どんなイベントになればと思ってますか? 今回原点回帰じゃないけど、みんなで同じ形の板をせーので彫ってもらって、出来上がり、どんなバラバラなものが出来るのか、自分の作品だけじゃなくて、他の人の作品も合わせて楽しんでもらえたらなと思います。 ー皆さん楽しみにされてますけど、ワークショップをする理由は加賀さんにとって何かありますか?わずか数時間ですが、実際にやってみると結構大変なんです。手が痛かったり、人によっては皮がめくれたり…全然思ってたのと違う、っていう方が多くて。木工には木工の、陶芸には陶芸の、ガラスにはガラスのひとつの作品の向こうにこういう大変さがあるのか、とほんのちょっとでもいいから体感して欲しい。一回やってみる事で物の見え方が変わってくると思うんですよ。ほんの数時間の体験で出来上がる喜びと物を作るのを仕事にしている人の作品の奥にある物、物の価値を知ってもらえたらと思っています。pan皿やonigiri皿とか、刃物ですーっと彫ってると思う方も多いけど、実際やったら固いし、ちょっとずつ彫ってひと彫りひと彫り進めて作るんです。これはやってみないと分からないし、知らないですもんね。その物の価値に気づいてもらうきっかけになればと思います。手を動かして物を作ることで得られる気づきの見え方、知ってもらう為にもワークショップは可能な限りやらせてもらってます。木工はワークショップにも向いてますしね。陶芸やガラスは時間とか、道具、炉が必要になってくるから工房に行かないとできないし、その点木工はどこでも出来るし、完成してすぐ使えるっていうのもいいですよね。 今回さろんぶるーで開催なので、自分が作った作品におにぎりのせて好きなところで写真とか撮れるし、楽しいんじゃないかな。
ーこれから加賀さんが未来に向けて挑戦、ビジョンはありますか? ん-、そうですね。あんまりおもしろくはないけど、今のペースを崩さずに続けていくことですかね。いつも言うんやけど、どーんと上がったら、どーんと下がるやん?うちは低空飛行でもいいから長く飛び続ける事を選んでいるから来年あれやって、10年後こうなって…ってあまり考えてないかもしれない。それよりは細々とでも自分の仕事をやるのが目標かな。 毎日毎日コツコツ積み重ねた結果、ああ、もう10年経った、もう20年経った、それでも続けてるっていうのが僕の中では理想ですね。それが一番最高なんかなって思えます。 僕が持っている武器は木工一個やし、それで長く続けていくためには派手な事はしないけど、それでも10年後も続けていられると幸せですね。 ー加賀さんにとって「瀬戸内」はどんな存在ですか?去年の企画展で出させてもらったプレート「凪」。そのイメージ。今は山の方に住んでるけど、それでも一時間ちょっと走ると牛窓とか日生っていって瀬戸内海がすごく近いし、嫁さんの実家も児島やし、高松にもちょこちょこ渡らせてもらっているし、でもいつ行っても凪いでるもんね、海が。荒れてるイメージがないから、それが結構好きな理由かな。あまりこう波がないっていうのがいいのかな。モノづくりの環境も岡山は晴れの国って言われるくらい木工に向いてますしね。あまり考えてはなかったんやけど、山陰とかは雨が多いし、晴れが少ないからもっと仕事はしずらかったかも。最終的に行き着いたところがちょうど自分に合った場所、タイミングや環境、色んなものに導かれたのかなと思います。
自然からもらった素材を感謝しながらカタチにする。忙しい日々の暮らしの中でシンプルだからこそ忘れやすい事を、ふっと思い出させてくれるような加賀さんの作品たち。3月の展示では真っ直ぐなものづくりと人柄に触れてみて下さい。
>>【展示会】加賀雅之 「木のうつわ展」 >>
続きを読む
vol.8 陶芸家 平岡朋美さん
たくさんの「こと」や「もの」があふれる今、作り手の想いと使い手の心がつながる奇跡。瀬戸内の小さな町で暮らし、ここにある風景、文化、素材と向き合い、ものづくりにこだわりと情熱を注ぐ作り手の方々をご紹介します。
彼らの美意識やものづくりの喜び、遊び心などが詰まった言葉を大切に集めてそれぞれのストーリーを発信していきます。
第8回は、陶芸家 平岡朋美(ひらおかともみ)さん。讃岐の空や海、自然の情景に魅せられて生み出された「讃岐blue」。色とりどりの器づくりについて、工房「朋花窯(ほうかがま)」を訪ねました。ー陶芸家になろうと思ったきっかけは何ですか?
短大を卒業してからシルクフラワーアレンジ(布花)の仕事を5年ぐらいしていて、その時にフラワーベースとなる花器やカゴをイメージごとに選んで作っていました。昔から、絵を描くことや布を使って洋服やぬいぐるみを作ることが好きだったんです。平面な作品より立体的な造形作品をつくり、使えるってことが好きでしたね。フラワーアレンジの仕事をしている中でベースとなる花瓶も自分の好きな形で作れるようになればいいなと思い陶芸教室に通うようになりました。
ーフラワーアレンジのひとつとして陶芸を始められたんですね。
陶芸教室が仕事場から離れた場所にあったので通うのが大変だったのですが、陶芸教室の伊藤先生が熱心な方で、だんだん陶芸をするのが楽しくなっていました。約2年ほとんど毎日のように通っていて今考えると結構迷惑していたんじゃないかな...。 そんな時に伊藤先生から「陶芸はやればやっただけ成長できる」「夢をかなえられるものだ」という言葉に半ば騙される形で(笑)陶芸家を目指すようになりました。今思えば夢もぼんやりとしていたし、陶芸は肉体労働だ~って事も分かってなかったなぁ。そして25歳の時に、フラワーアレンジの仕事を辞めて伊藤先生に弟子入りさせて下さいとお願いをしに行きました。でも、当時は地場産業が少なく陶芸品を販売できる所が無かったんです。生活もあったので、定期的にフラワーアレンジの仕事を委託で貰いながら陶芸家になるぞ!と思い込んで毎日鍛錬していました。30歳の時に工房を建て、31歳の時に窯を持つことが叶いました。家族もいきなり本気で工房?窯?って感じだったと思いますが、自分の力でやると決めた事ならと理解してくれて、精神的に支えてくれました。ー陶芸教室や展覧会に作品を出展されていますが器が出来るまでどれくらい時間が掛かるものなんですか?
土の状態から器となって窯から出てくるまでだと2ヶ月程かかります。土のブレンド→ロクロ成形→乾燥→デザイン→素焼き→釉薬(ゆうやく)がけ→本焼きの流れです素焼きは土が初めて火にさらされるので、ゆっくり水分を充分に抜きながらヒビ割れる事のないように、900℃迄14時間程焼きます。本焼きは手間をかけて何度もテストを繰り返したオリジナルの釉薬をまとった器物を1250℃まで36時間かけて慎重に焼く作業。釉薬が熱によってガラス状の被膜となり、水漏れを防ぎ美しい色の器になっていく。その為に窯全体の完璧に近い温度管理、酸素濃度の調整が必要です。様々な色の器を一緒の窯で焼くので、時には釉薬が溶けすぎて棚板とくっついて割れてしまう事もありますね。
ー窯での作業は聞いているだけでもヒヤヒヤします上手く完成出来るのはどれくらいの割合ですか?120%の仕事をして80%取れたら上出来ですね。焼きあがるまで窯も中はみれませんから、窯場の空気感、匂いなど経験上のカンの様なものが重要です。特に依頼された仕事の時は失敗できないですね。夜中、窯をたいている間で仮眠をとっているとき工房が燃えていたり、作品がマンガみたいにダラダラ~と溶ける夢を見た事あります.....悪夢です。ー平岡さんの作品では、青瓷(せいじ)の器が多く作られていますが作られたきっかけは何ですか?
弟子になってから最初の頃、師匠から釉薬はいろんな表現があるからまずは一つに絞った方がいいよと言われ、初めは紫色を表現したかったのですが紫は焼き物の伝統的釉薬の本筋と少し違うかなぁとなり、青色が好きだったこともあり青色が表現できる青瓷(せいじ)を選びました。
ー青瓷って高級で難しいイメージがあるのですけど...
初めは、技術的なものは何も知らずに決めましたね。青瓷って当時、陶芸家になった人が最後の目標にしていたり、お茶の世界でも青瓷器は牡丹や芍薬しか入れれない位の器だとお茶の先生方からきかされたり
ー別格なのですねお茶の世界や、中国で青瓷が生まれた歴史、日本に伝わった経緯等から、その様なイメージが定着している感じはありますね。選んだ私自身は後から学んだりして、そうだったのかぁ...って感じなのですが。青瓷は、他の釉薬の何倍もの量を器に重ね掛けし、1日で終わる事が1週間もかかることもあり、半分以上ダメになることもあって何度も心が折れました。だけど、青瓷を学んだからこそ釉薬の無限の可能性を知り、焼き物の幅広い世界に踏み込むきっかけにもなりました。今では、あの時青瓷を選んでよかったなと思っています。ー平岡さんといえば「讃岐の色」とイメージするのですが「讃岐blue」は実際に香川の材料が入っているのですか?地元香川の景色を表現するなら香川の土を使わないと意味が無い気がして日本の焼き物の歴史はその土地で採れる土や石、それに適した加飾等が伝統として受け継がれています。焼き物材料店で釉薬を買って色を出すことも出来るけど、産地では無い香川でも自身のオリジナルにこだわりたい。これは師匠から受け継いでいる事でもあります。
ーご自身で土を採ってきていると聞いたのですがはい、焼き物に適した土は香川に少ないので、土では無くて釉薬材料となる凝灰岩(ぎょうかいがん)を採りに。師匠やそこで学んでる人、数人でハンマーやスコップを持って山へ。これが、めちゃくちゃ重労働なんです。それを持ち帰って機械で細かく砕いた粉末を長石や灰等と混ぜ合わせていきます。 ー大変そう...青瓷釉の青はそこから生まれているのですね。凝灰岩の中には鉄分が含まれていて、青瓷の青を引き出す為の3%程の必要量とぴったりなんです。正に香川の山に眠ってる鉄が窯の中で土と合わさって出来る色なんですよ。土によって発色や貫入(かんにゅう)のひび割れ模様が変わるため、窯たき毎に、作りたい色や表現を目指して土や釉薬の調合をしています。自然のものは安定しにくいので研究や試作を繰り返し、生まれるのが「讃岐blue」の器なのです! ー作品の形や色のインスピレーションはどこから生まれているのですか?自然界から来ていますね。日々の空、花の色や昆虫、色深海生物の不思議な形や色調も好きです。陶器に使っている釉薬にも自然の中から生まれた鉱物が溶け合わさって色となっていますからね。窯の中で器の色が変わっていく窯変(ようへん)という現象があるのですが、思ってもみない色が現れるんです。空の色が毎日変化するのと同じ景色に感じますね。細密な計算やデータの元、生まれた色とそんな自然の偶然から生まれた色、どちらも表現したいと思っています。 ー海外にも行かれたのですね。
タイとフランスに文化交流の一環で参加したことがあります。タイの時は、初めての海外展示で体調面も万全ではなく前準備も足りなかったですね。また、陶芸に対する日本とタイの捉え方かなぁ..そんな違いもあり自分が思う表現が上手く出来なかった気がしています。ー苦い経験になったんですね。タイでの経験から、次のフランスでは準備万端で絶対に後悔しないよう、結構こだわって挑みました。
フランスのトゥールに行った際は、香川の伝統工芸のものづくりを伝える匠雲(たくみくも)さんのチームの一人として盆栽や和菓子、ツアーで回ってきた観光客のお客様にお茶をたてるワークショップなど日本の文化体験を取り入れました。頑張った甲斐もあって、器が欲しい!気に入ったと声をもらい、向こうのギャラリーの方とも良いご縁を頂き今に繋がる経験が出来ました。フランスに行くことで、自分の作品が認められたように感じましたね。ずっと見守って応援して頂いた方からもフランスに行って良かったね、ちょっと変わったよねと言って貰えてなんだか殻が剥けて新しい自分、もう一人の自分に出会えたような気がしました。
ー今回の展示で布作家のさとうゆきさんとのコラボした作品が出来ましたがコラボのきっかけは何ですか?今回の展示では、お抹茶盌(まっちゃわん)を様々に展示します。両掌におさまるサイズ感の中で、色、形、デザインの展開を広げている。制作にハマっている器。器を手で包み込みお茶を飲むことは日本人特有の文化ですよね。難しいイメージのお茶ですが、もっと気軽にお茶を楽しんで貰いたいですよね。これさえあればお茶が出来る!おままごとのようなお茶セットを作ろうと考えていたところ前々から気になっていたゆきさんの布巾着「ころん」がお茶のセットを包むのにピッタリじゃないかと思いました。ギャラリーの展示会で初めてお会いする機会がありまして「運命」だと思いましたね(笑)ーとっても楽しそうなコラボになりそうですね。毎日使って頂きたい器を優しく包み込んでくれる素材として、ゆきさんの布作品はピッタリ!布袋の紐を解いて器を覗き見てわぁっと驚き、布から取り出して小さな蓋つきの器には金平糖なんか入れてみようか..なんて。良いですよね。布の色やスティッチの色などこだわった部分があるのでゆきさんとのコラボ完成が楽しみなんです。器が私の手を離れて皆様の日々毎日の日常の道具として自分らしいお茶時間を過ごして貰えたら嬉しいですね。
ー同時に開催されるお茶会について教えて下さい。私が作ったお茶盌に茶筅(ちゃせん)を使い自分でお茶をたててもらって混ぜて飲む所作、一連の流れと時間を愉しんでほしい。毎日のお茶やコーヒーを飲む時間と同じように気軽に取り入れて貰いたいと思います。ノアイエさんの和菓子も独自のスタイルを生みだしていて、愛らしい表情と口に入れた際のちょっとしたインパクト..とても楽しみ。茶筅さばきも改めて教えて頂こうかと。暮らしの中の身近なスタイルのひとつとして器を介して体験してほしいですね。お茶の時間って気持ちの切り替えになると思うんです。お茶の所作って難しく感じていますが思いやりの所作だと思っています。だから難しく考えず気軽にお茶会ごっこを楽しんでくれたら嬉しいです。ー平岡さんにとって「瀬戸内」とはどんな存在ですか?私にとっては「ゆりかご」のような場所で大切なことを忘れないでいれる場所です。子どもの頃は島に住む祖父母の元で夏を過ごしました。青い海、塩の香りを嗅ぐと、島の人たちの優しさや純粋さを思い出して、まるでふわふわの布に包まれるような「ゆりかご」のようで。純粋に自由に作品が作れているのは、周りの人たちの支えがあってこそですね。40代ぐらいの頃は生まれ変わったら陶芸はしませんと言っていたんです。でも50歳を迎えて、もっといろんなことをやっておけばよかったと思いましたね。今は、100歳まで生きても足りないんじゃないかと思い初めまして...若返りの薬が欲しいです。自然環境が崩れてきている今、美しい瀬戸内の情景を思い出と共に大事にしたい、作品に表現していきたいなと思っています。美しいものを見て、作品に表現する。それを見た人が自身の記憶に残る思い出、美しい景色を思い返す。次の世代の方たちにも繋がっていって、この空や海を守っていきたいと思えるような意識を継承できるような形で器を生みだし残していく事が出来たら、と思います。
今回は、讃岐の色に魅せられた平岡さんの妥協しないまっすぐな作品への情熱を感じるお話でした。平岡さんの力強く、女性らしいしなやかな形と美しい情景、その一瞬を溶かした色を取り込んだ魅力あふれる器たち。10月から始まる展示会をぜひ楽しみにお待ちくださいね。
>>【展示会】ART&LIFE 平岡朋美2つの陶展~讃岐に染まるうつわたち~<<
続きを読む
vol7. Rie Glass Garden 杉山利恵さん
たくさんの「こと」や「もの」があふれる今、作り手の想いと使い手の心がつながる奇跡。瀬戸内の小さな町で暮らし、ここにある風景、文化、素材と向き合い、ものづくりにこだわりと情熱を注ぐ作り手の方々をご紹介します。彼らの美意識やものづくりの喜び、遊び心などが詰まった言葉を大切に集めてそれぞれのストーリーを発信していきます。第7回は、讃岐の山からうまれた庵治石をガラスに溶かしたら瀬戸内海の色になったAji glass。香川の温暖な気候から生まれたオリーブをガラスに溶かしたら瀬戸内の風の色になった Olive glass。
長い研究と実験を重ね地元、香川から誰もが誇れるガラス作品を生みたい!と思い、地場の産物を溶かし込んだガラスを生み出した、杉山利恵さんの工房を訪ねました。
―ガラス作家になったきっかけは何ですか?小さい頃から、玩具の一部としてビー玉や空瓶を集めるのが好きでベットの頭からどんどん広り部屋中に空瓶を並べてました。何も考えずに集めていたガラスが、昔は趣味のひつだと勘違いしていましたが 実は自分にとって特別な存在で、無意識に執着していたことが振り返ると解ります。―ガラスが特別になったきっかけはなんですか?たまたま入った地元のギャラリーで見つけた地元のガラス作家さんの作品「香川でもガラスが作れるんだ!」お店を出た瞬間すぐに連絡をして工房を紹介してもらったのがきっかけです。紹介された工房に入った瞬間「これがしたい!!」と直感で強く思ったんです。その時すでに、趣味ではなくプロになるためにスタートしたいと感じていました。 が、現実問題も色々とあり…まずはとにかく早くガラスを触ってみたい!
ということで土日に開催されるガラス講座を受けようと、 土日休みの職に変え、講座に通い始めました。最初に触ったガラスの感触は今でも忘れられません。ガラスを巻き取り紙(紙りん)で触っただけで楽しくて、楽しくて…まだカタチになってなくても、熱に柔らかく赤いガラスを見ているだけで、 楽しくて仕方なかったんです。―ガラス教室からガラス作家へ、すぐにガラスの道に入ったのですか?
出会ったのがそろそろ30代になるかなって言う時期で、このまま趣味に留めたら歳を取った時後悔するんじゃないかなって…ちょうどその頃母を亡くしたこともあり、立ち止まって考えることができました。母も物づくりがすごく好きで、父も農業を営んで作物を作っている私にも、物づくりをする両親の血を受け継いでいるんだと感じました。今からでもやってみよう!と資金を3年かけて自分で貯めて、東京の学校に行き、1年で吸収して帰ってこようと思っていました。でもとても1年じゃ足りない…もう少し勉強したいと思い富山の学校に2年通うことになりました。
―地元香川の庵治石との出会いは?自分の作風を探っている時期に、もともと地元愛は強かったけど東京と富山の学校の時期に外から見た香川の魅力を再発見しました。平和で、穏やか、空気も全然違うんです。香川で育った農作物を食べ、豊かな土壌で育った自分が香川から生まれるものを作りたい。 ガラスにも香川のものを食べさせたら自然と何か伝えてくれるんじゃないかなと考えたんです。地元らしさが出るガラスを作れたら、自分のことも表現できるし、香川を表現できる。一石二鳥かも!とワクワクしました。
そこから、溶かせる素材を探し始めました。
―庵治石に行き着いたのはどうやったんですか?香川にはいろいろな素材がありますが、まず可能性の高いものからやってみよう! と最初に試したのが香川が誇る庵治石でした。というのも、一般的にガラスの着色につかわれるのもコバルト・鉄・銅などの鉱物だからです。天然の石を溶かせるかどうかなんて、全く判らない状態からのスタートでしたけど。
友人に石屋さんがたまたまいて「庵治石」のいろんな欠片や石粉を送ってもらいました。初めは全然溶けず、グレーの汚い色になり失敗しましたが、 2年に一週間だけの材料学の先生の特別授業があって、放課後先生に根掘り葉掘り聞きまくりました(笑)
そして一度だけ小さな実験を一緒にしてくださり、小さなおはじきみたいなガラス玉から水色が出て…それはもう鳥肌がたちましたね。
実験を重ねてだんだん水色が蒼くなってきて… 庵治石からこの蒼色が出ることに涙が出るほど感動しました。
―最初から庵治石にチャレンジしたんですね!?他にもリストアップだけはしたんですよ、でも消去法というか、勘がいいのかもしれないです(笑)。鉱物だから熱にも強く、何か出る可能性があるかなって。結構せっかちなんです!ガラス自体そうですが、結果がすぐに見えるじゃないですか(笑)。漆とかは完成までめちゃ長い…とても自分には出来ないです。
―庵治石から蒼が出て、それからどうしたんですか?まず庵治石の組合や石の地主さんに、材料や「庵治石」という名前自体を使ってもいいですかと、 お伺いを立てに挨拶回りしました。すると思わぬ反応が返ってきたんです。庵治石から出る廃材を使って、こんな色のガラス製品になって…とても良いと思うよ!どんどん使って香川と庵治石をPRして下さい!
と応援してくださったことがとても嬉しかったです。何より産地の方が喜んでもらえるのが。
そこから地元の反応も見たくて、県産品コンクールに応募しました。そしたらまさかの賞をもらえまして…(笑)初めて県内外の方の目に触れてもらえて「瀬戸内の色だね。」「庵治石からでた色なんだね!凄い!」って。生の感動の声を聞けたことが一番嬉しかったし、励みになりましたね。
―じゃあ、結構順風満帆ですね!
それが、ガラス工房を個人で構えるのってとっても大変なんです。普通はまずどこか、ガラス工房に勤めて数年経験を積んでから独立したり工房をレンタルして制作する作家さんも多いのですが、私の場合は在学中に賞を戴いてしまったためにメディアにも取り上げられて、仕事も来る、取材も来る、でも工房は無い…そんな後押しもあり、すぐに工房を立ち上げるきっかけになりましたが、最初の1年はめちゃくちゃ辛かったです。学校を出たからってすぐいい作品なんか出来ないんですよ。10個中1個しか上手くいかない。でも、いきなり高松三越の展示に出さなくちゃいけない…在庫も無いから、ひたすら作っては作品になる物を選び、毎日補充しに行ってましたね(笑)。
―そんな苦労があったんですね!庵治石の作品を作れるようになって、去年発表したオリーブガラスとの出会いもやっぱり地元愛からですか?オリーブとの出会いは5年くらい前に、香川のオリーブ園SOUJUさんが持ち込んでくれました。オリーブを燃やした灰を持って工房に来てくれたのが、きっかけです。熱に弱い植物は無理だと思っていたので無理だと思いますよ。と言いつつ、一度やってみました。やっぱり色が出なくて…結果を伝えたら「量が多かったら、出ますかね?」と再度持ってきてくださったんです。そしたらたまたま2回目で緑色が出ちゃったんですよ。あっけにとられましたね。「緑の物から緑が出た!凄いな!」みたいな。でも次に実験するとまた色が出なくなったんです。同じ配合にしても出ない(苦笑)。庵治ガラスとは勝手が違いましたね。必死に緑を探しましたよ。夜中に心配で何度も工房に行っては色を確認したり、失敗した壺のガラスを全て掻き出したり… とっても苦しみました。―庵治石とは違った苦悩ですね!色が出ても全然安定しないんです。フレッシュなグリーンが出たかと思えば、濃い茶色気味のグリーンだったり…同じ色を出そうと何度も何度も試して、ふっと思ったんです。オリーブ本来の色って何だろうって。葉っぱの裏と表、季節でも緑の色合いが違うじゃないですか、実の色も変わっていきますし…オリーブガラスにムラがあるのもオリーブ本来の姿なんじゃない?って。同じ色を並べてみた時に、なんだか物足りなささえ逆に感じてしまって、 オリーブは色が違うべきなんじゃい?って。そう思ってたくさんの緑を並べるとオリーブの景色が広がりましたね。―その頃でしたっけ?去年の県産品コンクールに応募してて、何だか切羽詰まってましたよね?そう、「もうやるしかないじゃん!」みたいな。県産品コンクールに応募して自分を追い込みました。もう腹を括りましたね(笑)。何だかいつも、そんな人生ですね!周りの人や物事に、ありがとう!って。急かしてくれてありがとう!って。そもそもは自分で追い込んでるんですけどね。今は無理して良かったなって思います(笑)―子育てみたいなものですね(笑)。まだ息子の方が育て易いですよ(笑)子育てよりオリーブガラスの方が大変!全然言うこと聞いてくれない!でも答えはあるんですよ、その色その色が出る場所があるはずなんです。科学ですからね(笑)。でも私がまだ行き着いて無いだけなんです。一生かけて色をコントロールできるようになってみたいです!まだまだ振り回されてばかりですけど…―手間かかる子ですしね(笑)。そう、めちゃめちゃ時間と労力かかるんですよ。枝葉を車やトラックにいっぱいいただいて帰って、乾燥させて、切り刻んで、燃やして灰にして、ふるいにかけて…細かい異物を取り除いてあげる。ここまでしないと綺麗なガラスにならないんです。自然のものを扱うって本当に大変ですよね。庵治ガラスはどっしりとした落ち着いたお兄ちゃんでオリーブガラスは手のかかる妹です(笑)。
―そんな大変なオリーブガラス、特別に何か作りたいものはありますか?実はすでに試作してるものがあるんです…オリーブだからこその物を作りたい。今回のオリーブガラス展に出す予定なので、ぜひ楽しみにしていて下さい!―それはとっても楽しみですね!今はまだ内緒なんですね…では、杉山さんにとってガラスの魅力って何ですか?「現実離れしてる存在」かな。透かして見ると向こうの景色が歪んだりして、世界が違って見える!―今後ガラスに限らずやってみたいことはありますか?海辺のカフェをしてみたいです!以前海辺で展示をしたのですが、 海を背景にガラスを置いてると、ここにあるべきなんだな、って。この蒼と緑のガラスは特別、水を入れるとめちゃめちゃ綺麗なんです。一番綺麗に見える場所で使っているところを見たいですね。―今回の展示への意気込み、見どころを教えて下さい。私のガラス人生第二章でもあるオリーブガラスが持つ色んなグリーンの色!色んな色合いが並ぶ展示会ならではの風景を見て欲しい!そして新作もあります!
―苦労もあったと思いますが、何だかとっても楽しそうですね! 最後に杉山さんにとって「瀬戸内」とは?母のような温かい受け皿!空気の母性。お母さんのお腹の中のような、もう覚えてないですけど(笑)何か守られてる温かさを感じます。
今回は、ガラスと向き合い自然が織りなす作品の制作秘話でした。杉山さんの情熱と長い研究が生み出したAji GlassとOlive Glassは庵治石とオリーブ、そして杉山さんの心が溶け合わさって生まれた色なのかもしれませんね。オンラインショップにてAji Glass、Olive Glassのお取り扱いがございますのでぜひご覧になってくださいね。
続きを読む
第6回は、kitahama blue storiesでも絵本が子どもから大人まで大人気、高知県在住の絵本作家 柴田ケイコさん。最近では人気のTV番組「セブンルール」でも取り上げられるなど、全国で注目が集まっています。絵本作家になられたきっかけや作品づくり、これからのことなどをお伺いしました。
続きを読む
砥部焼のスギウラ工房 杉浦綾さん。伝統工芸品の砥部焼に斬新で愛らしい作家の手仕事がプラスされた、暮らしにしっくりと馴染む器を作られる陶芸家です。 杉浦さんとの出会い、個性あふれる作り手が暮らす街、愛媛県大洲の方々とのご縁でつながり、オリジナルで可愛いカモメの箸置きを作っていただいたのがはじまりです。
続きを読む